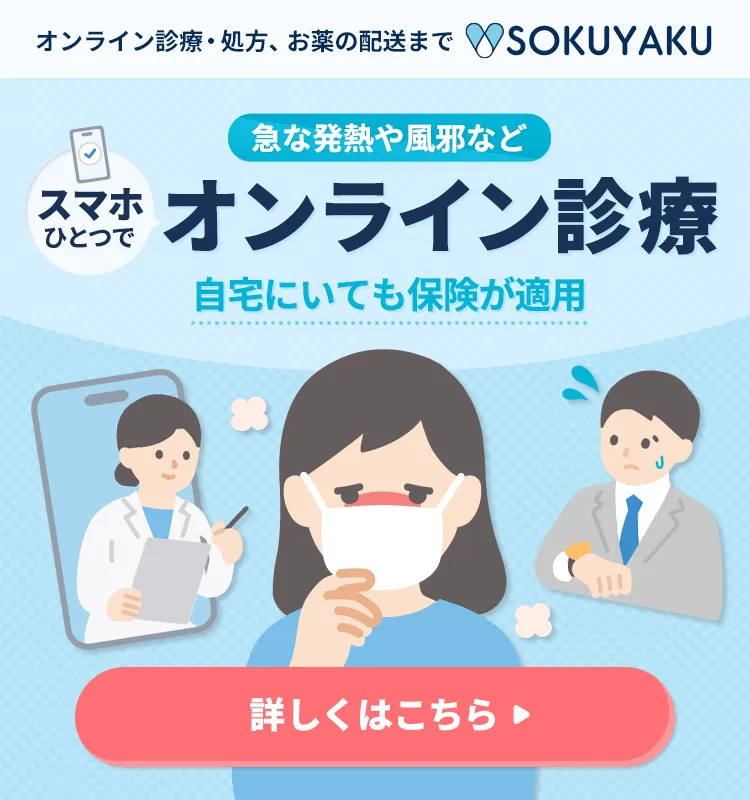「食欲不振」症状の「歯が痛い」に関する一般歯科で診療可能な病名一覧
再石灰化
歯の再石灰化とは、唾液に含まれるカルシウムやミネラルの濃度が高まることで歯の表面のエナメル質が修復されることを言います。しかも、溶かされたエナメル質をただ修復するだけでなく、結晶の構造を変化させる...
過剰歯
過剰歯とは、通常よりも多くの歯がある状態のことです。子どもの虫歯治療などでレントゲンを撮ったときに発見されることがあり、現れる場所は上あごの2本の前歯の間と上下の親知らずの後ろが多いとされています。...
歯槽膿漏
歯槽膿漏とは別名を歯周病とも呼び、歯の習慣病とも言われています。若い頃は歯の病気の自覚症状が全く無くても、実は着実にゆっくりと歯肉が衰えていっており最終的には歯がぐらつき抜けてしまいます。抜けてし...
智歯周囲炎
智歯周囲炎とは、親しらずの周辺に起こる炎症のことです。他の歯にはない、隣の歯との間に隙間があるため、炎症が起こり、様々な症状がでます。原因はこの歯と歯の隙間に細菌が溜まり、感染症を起こし、腫れや痛...
知覚過敏症
知覚過敏症とは、冷たいものや暖かいものを口に入れたときに、歯に痛みを感じる症状のことです。主に痛覚などの知覚神経を刺激することによって生じます。原因は様々なことが考えられますが、歯が摩耗したり擦り...
歯根嚢胞
歯の根っこの先端部分に膿がたまった袋ができてしまう状態を歯根嚢胞といいます。神経が死んでいる、または神経を取った治療済みの歯にしかできません。神経があった場所または死んだ神経そのものに細菌が繁殖し...
むし歯
むし歯とは、口腔内の細菌が酸によって歯質を脱灰することによって起こる、歯の欠損のことを言います。細菌は糖質や乳酸を分解して酸を産生し、細菌と食物残渣と唾液によって発生した歯垢と合わさると口腔内は酸...