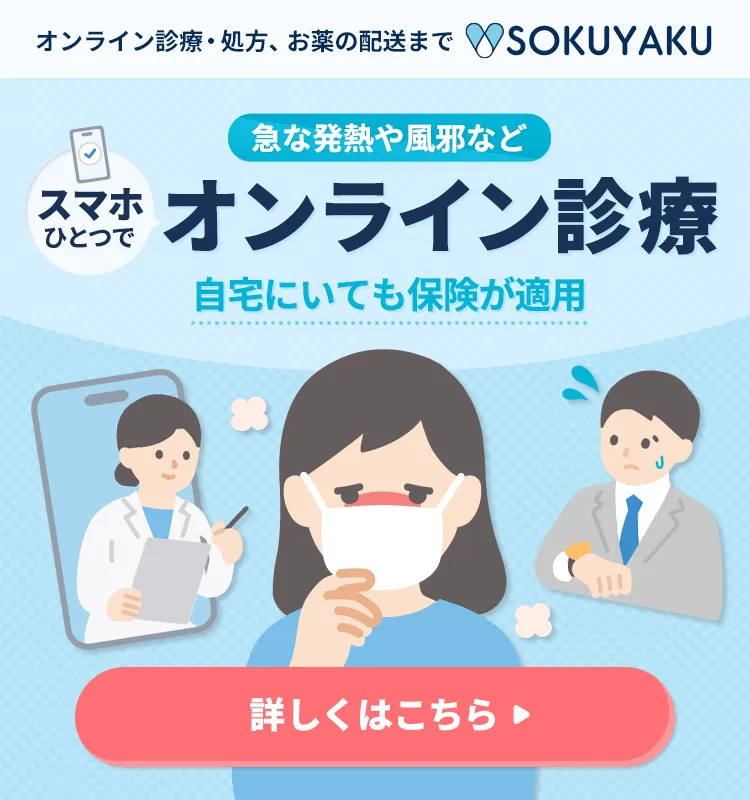アナフィラキシーはどんな病気?
アナフィラキシーとは、ハチ毒や食物、薬物等が原因で起こる、急性アレルギー反応の一種です。アナフィラキシーは、じんましんや紅潮等の皮膚症状や、ときに呼吸困難、めまい、意識障害等の症状を伴うことがあり、血圧低下等の血液循環の異常が急激にあらわれるとショック症状を引き起こし、生命をおびやかすような危険な状態に陥ってしまうことがあります。
これをアナフィラキシーショックと呼びます。
アナフィラキシーを引き起こすきっかけには、ハチ毒アレルギー、食物アレルギー、薬物アレルギー等があります。最近では、この他にもラテックス(天然ゴム)によるアナフィラキシーも注目されています。アナフィラキシーは、症状が急激にあらわれることから、即時型アレルギーに分類されます。花粉症やアレルギー性鼻炎、気管支喘息等も即時型アレルギーに入りますが、アレルギー症状があらわれる部位は鼻や気管支等、疾患により限定されています。それに対し、アナフィラキシーの場合は全身にアレルギー症状があらわれるのが特徴です。
アナフィラキシーの主な症状は?
アナフィラキシーが起きると全身に症状が現れます。最も多いのが皮膚症状、次いで呼吸器症状、粘膜の症状、消化器の症状、循環器の症状も見られます。
全身に急激に症状が現れるのもアナフィラキシーの特徴です。
皮膚症状にはじんましんやかゆみ、呼吸器症状には咳、喘鳴、呼吸困難、粘膜の症状には目のかゆみやむくみ、消化器系の症状としては吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などが代表的です。アナフィラキシーは重篤な場合、全身の血圧低下や意識状態の低下を引き起こし、命に係わることも少なくありません。急激な血圧低下は意識を失うなどのショック症状を引き起こすことがあり、極めて危険な状態と言えます。
原因と疑われるものに触れたり、食べたりしてから症状が現れるまでの時間はさまざまです。数分~数時間の間に症状が現れる場合は、薬や蜂毒などの直接体内に入るものが原因となっている場合が多いです。対して食べ物が原因の場合、消化吸収されるまで時間がかかるため薬や蜂毒などと比較すると発症までの時間が長いと言えます。
アナフィラキシーの主な原因は?
アナフィラキシーはアレルギーの原因となる物質に触れたり食べたり、吸い込んだりすることで起こります。原因物質として最も多いのが食べ物、次いで蜂などの昆虫類、薬剤などがあります。
原因となりうる物質は多く、食べ物なら鶏卵、牛乳、小麦、そば、ピーナッツ、甲殻類などがあり、これらの食物アレルギーは幼児に多い傾向があります。食べ物のアナフィラキシーには、原因となる食べ物を食べ、さらに運動をすると症状を引き起こす食物依存性運動誘発アナフィラキシーという特殊なものもあります。
スズメバチ、アシナガバチなどの毒液によるアナフィラキシーショックは日本では珍しくなく、毎年亡くなる人がいます。
薬物のアレルギーに多いのは抗菌薬、解熱鎮痛剤、検査で使用する造影剤、局所麻酔薬などがあり、輸血が原因となることもあります。また、近年注目されているラテックスアレルギーは天然ゴム製品に触れることで反応が起きます。風船や避妊具、ゴム靴など日常で使用するものにも天然ゴムが使用されているため、アレルギーがある方は注意が必要です。
アナフィラキシーの主な検査と診断方法は?
アナフィラキシーの原因となるアレルギー物質を検査するために、血液検査や食物経口負荷試験を行います。血液検査では血液の中にある抗体を調べ、アレルギーの原因となる物質を絞るこむことができます。原因となる物質がある程度絞れたら、皮膚にアレルゲン液を付け専用の針で小さく傷をつけて皮膚の赤みや腫れを確認します。
これによってアレルゲンとなる物質を判定することができます。その後は食物除去で症状の回復を確認した、少量を一定間隔食べる食物経口負荷試験などを行うことで耐性獲得や、リスクの評価を行います。原因となる食べ物やリスクが分かればアドレナリン自己注射薬などで万が一に備えることができます。
アナフィラキシーショックを発症した場合には意識、呼吸、血圧や血中の酸素濃度を測定し迅速な治療を開始します。急激に症状が進行するリスクがあるため、疑いがあるという段階で治療を行い、症状が落ち着いてから上記のような詳しい検査を行う場合が多いです。
アナフィラキシーの主な治療方法は?
アナフィラキシーの強いショック症状が起こった場合、アドレナリン注射や酸素投与、輸液などを用いて治療を行うのが一般的です。アナフィラキシーショックを起こすリスクがあるとされている場合、アドレナリン自己注射薬を携帯することで緊急時に備えることができます。
症状が現れた際に即座に注射ができ、アナフィラキシーを回避することができます。
また、軽い皮膚症状や粘膜症状には抗ヒスタミン薬、呼吸器症状には気管支拡張薬など症状に合わせた薬が使用されます。
症状が進むと経口副腎皮質ステロイド薬などを使用する場合もあります。
また、薬物アレルギーを防ぐには、アレルギー症状をおこした薬を二度と使用しないよう医師にも共有することが大切です。
名前がちがっていても同じような作用をもつ薬は多く、医師の処方を受けるときは注意が必要です。食物アレルギーも同様で、日常生活での注意が必要になるためあらかじめ学校や職場に緊急時の対処法を共有しておくことも必要です。
アナフィラキシーの初診に適した診療科目
- アレルギー科 ( アレルギー科の病院一覧 )