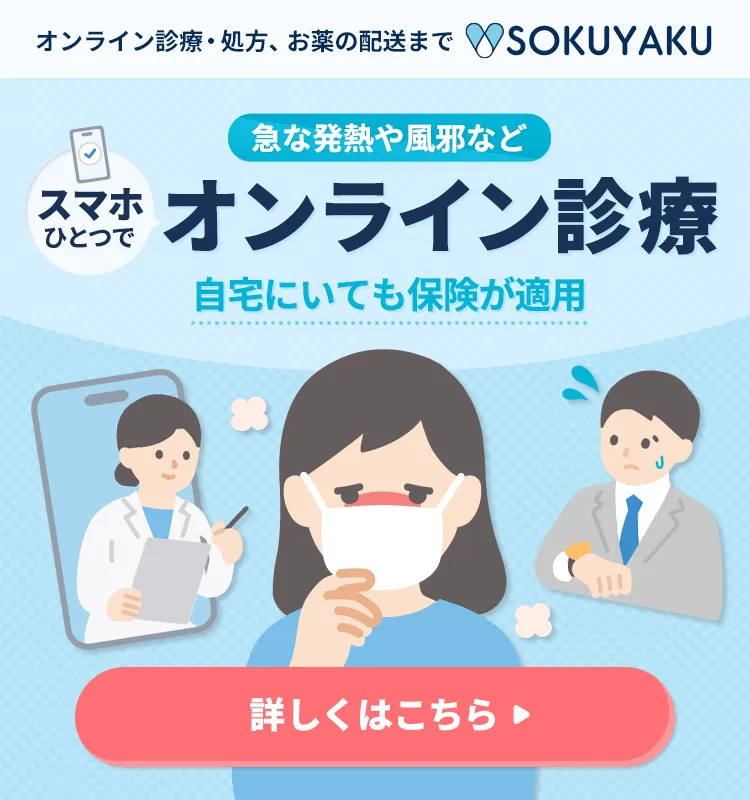慢性化膿性中耳炎はどんな病気?
急性中耳炎で鼓膜に穴が開き急性炎症はおさまったものの、鼓膜の孔が残り続ける病気を慢性化膿性中耳炎といいます。通常はあいた穴は自然に閉じますが、中耳炎を繰り返したり、治り方が不十分だと、この穴が閉じなくなり慢性(化膿性)中耳炎になります。
種々の程度の難聴を引き起こすやっかいな慢性化膿性中耳炎の多くは、大人にみられます。 幼少期に急性中耳炎にかかり鼓膜穿孔を起こしたものがそのまま慢性化することが多いのですが、幼少期にはあまり耳の病気に気付かずに大人になって発症する場合もあります。
大人になってから発症する慢性化膿性中耳炎は、糖尿病や甲状腺の病気、進行がんやエイズなどで免疫力が低下することに関係していると考えられます。 しかし病変としては比較的軽いケースがほとんどです。
慢性化膿性中耳炎は、痛くない中耳炎です。治療には手術を含めて長期にわたる根気よい治療が必要です。ところが痛みがないため、聴力の回復を強く望まない人の仲には、病院に行くのが面倒という理由から病気をそのままにしてしまうこともあります。放置しておくと感音難聴が進行したり、まれに顔面神経麻痺、脳腫瘍などに発展する場合もあるので、症状が進行または悪化するようなら耳鼻咽喉科を受診したほうが良いでしょう。
慢性化膿性中耳炎の主な症状は?
穿孔(せんこう)と呼ばれる鼓膜に空いた穴に細菌が入り、うみが生じ耳の中がじくじくした状態です。このじくじくしたうみは、耳だれまたは耳漏(じろう)と呼ばれます。鼻がつまる、鼻汁が出る、喉に痛みを感じ、咳が出るなどの症状が始まり、耳の痛みを伴い始めます。乳幼児の場合は、39度以上の発熱を伴う場合も多いです。
穿孔が原因で伝音難聴という症状が出てきます。伝音難聴とは、音がきちんと伝わらない状態です。穿孔が小さい場合は、聞き取りにくさはまだ軽度ですが、穿孔が広がっていき感染した状態が続くと耳の中にある神経にも広がってしまいます。そうなると、感音難聴という症状を引き起こします。
感音難聴は、蝸牛と有毛細胞の機能的問題により聞こえにくくなる状態です。耳鳴りが起きる状態では聞こえがかなり悪くなっています。
症状が進むと、耳漏が出ているために中耳圧が緩和され耳の痛みが軽減されますが、難聴が進んでいる状態ですから治療が必要です。乳幼児が痛みが軽減し泣きじゃくることがなくなり、放置してしまう可能性があり難聴が進む危険があるため、聞こえているかどうかを確認しましょう。
慢性化膿性中耳炎の主な原因は?
慢性化膿性中耳炎の原因は、鼻や咽頭から細菌やウイルスが入り、耳管や外耳道から鼓膜を通過して感染することです。菌やウイルスが入ったからといってすぐに感染が生じるわけではありません。
免疫力の低下により、防御システムがうまく働いていないことで、菌やウイルスによる感染が生じたと考えられます。
そのため、免疫力が低下する病気、例えば糖尿病や甲状腺の病気、エイズなどにかかっていると慢性化膿性中耳炎にかかりやすいです。また癌で化学治療をしている場合にも免疫が低下しがちです。中耳炎になった時にきちんと治療を終えていないと特に免疫が落ちた際に発病しやすくなります。
乳幼児時代に中耳炎にかかったことのある人は、治療が完璧ではない場合に起きるため注意が必要です。特に中耳炎に複数回感染し治療した経験のある人は、大人になってから慢性可能性中耳炎に罹患する可能性が高いです。
炎症が長引くと中耳内にある小さな骨である耳小骨を損傷してしまい難聴になってしまいます。
また痛みがないからと放置しておくと顔面神経麻痺や脳腫瘍を引き起こしてしまうことも。
慢性化膿性中耳炎の主な検査と診断方法は?
最初にする検査は耳鏡検査で鼓膜に穴が開いているかどうかを確認し、鼓膜が腫れて炎症が起きてるかどうかを確認します。耳鏡は、患者の耳の大きさに合わせて数種類あり直接耳に入れて中を覗きます。
拡大耳鏡や光源を持ち内部がよく見える直視耳鏡などもありますが、視覚だけでは急性中耳炎と慢性化膿性中耳炎を区別できない場合も少なくありません。
その場合は、ティンパノメトリー検査が適用されます。
ティンパノメトリー検査とは、耳の穴に専用機器を当てて鼓膜に陽圧・陰圧をかけて鼓膜の動きを観察する検査です。鼓膜の下にうみが溜まっていると鼓膜の動きが鈍くなることを利用しています。またどのような菌やウイルスに感染しているのかを検査することも必要です。
細菌検査は鼻孔から鼻の奥の細菌を採取する方法と鼓膜の一部を治療を兼ねて切り取る方法があります。どのくらい患部が広がっているかは、X線やCTを利用して確認します。
痛みがなくなっていても聴力検査をしておきましょう。すぐに治療すれば聴力が回復する可能性が高いです。少しずつ低下する聴力は気づかないうちに難聴になっている場合も少なくありません。特に乳幼児は聴力検査が必要です。
慢性化膿性中耳炎の主な治療方法は?
鼓膜の裏側に当たる中耳腔(ちゅうじくう)に溜まっているうみなどの分泌物を除去し、抗菌剤を内服したり、点耳薬を挿入して耳だれをとめることで感染を抑えます。しかし、そのままでは穿孔が残った状態です。穿孔は自然に消える場合もありますが、3ヶ月ほど待っても穿孔がふさがらない場合は手術が必要です。
鼓膜の穴を閉じ、鼓膜を再生することで難聴を治癒します。耳鳴りなども鼓膜再生により治療可能です。穿孔があまり大きくならないうちにすると、聴力が回復しやすいため早めの治療をしましょう。
手術は2種類あります。鼓膜形成術は、局所麻酔ででき、入院も短い期間です。耳の後ろの皮膚から皮膚組織を採取して穿孔を閉じます。
穿孔が大きい場合は、それだけでは不十分で中耳機能が回復しないことが多いです。
その場合は、鼓室形成術をしなくてはいけません。鼓室形成術は、鼓膜の形成を行う手術で、全身麻酔でする手術です。これらの手術は年齢的な制限はなく、高齢者も対応しています。
慢性化膿性中耳炎の初診に適した診療科目
- 耳鼻咽喉科 ( 耳鼻咽喉科の病院一覧 )