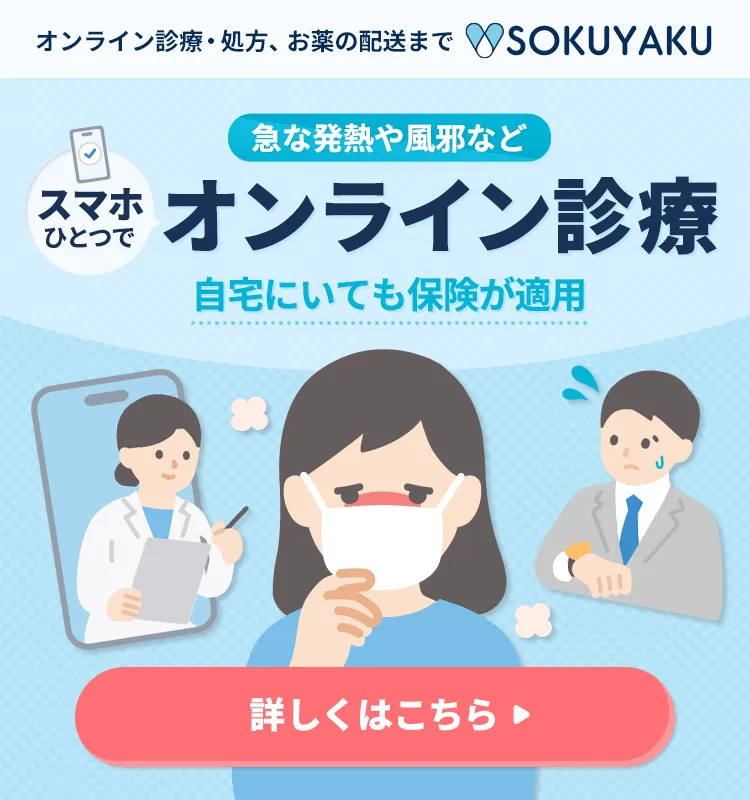不附随運動はどんな病気?
不附随運動とは、脳からの神経伝達がない状態で運動を起こすことです。一般的には心臓や腸などの内臓が意識せずに働き続けていることをさします。熱いものに触れた際に咄嗟に手を引っ込めようとする脊椎反射もこれに属します。内臓の不附随運動は、絶えず行われている場合が多く、通常の筋肉とは異なった筋肉が働いており、基礎代謝の一部になっています。
不附随運動の主な症状は?
不附随運動とは心臓の収縮や消化管のぜんどう運動、消火液の分泌など、自分の意思とは関係なく起こる運動のことです。これらは健康体において常時起こりますが、一方で緊張状態や脳に障害がある場合、薬物を服用した場合にも不附随運動が見られます。症状は手足の振えや痙攣、異常な姿勢、口周辺や舌の異常運動、手足や体全体を振り回すしぐさなどがあります。
不附随運動の主な原因は?
事故や怪我による外的要因や、薬物乱用などによる中毒症状の後遺症として、脳の血管に障害が起きたことが原因で、正常な運動能力を司る脳部位の機能が不全となり、不附随運動は起こります。脳の信号が正常に伝わることが阻害されるため、筋肉の収縮運動が異常な動きを起こすのです。パーキンソン病の罹患が原因で不附随運動が発症することもあります。
不附随運動の主な検査と診断方法は?
不附随運動の多くは持続的に出現しているため、検査方法としては実際の観察が有効ですが、一部は突発性ないし間欠的に出現するため、患者本人もしくはその家族から、詳しく聴取することが一般的です。不附随運動に関する検査に中で最もポピュラーな手段が表面筋電図による記録です。その際は、出来るだけ複数の筋から記録を取ることが必要で、場合によっては脳波を同時に記録する事が効果的です。
不附随運動の主な治療方法は?
不附随運動の治療法は、場所によってかなり違う傾向にあり、薬物療法で治ることもあれば、現代医学では対応できないケースがあります。アロチノロール、クロナゼパムなどで治療可能なこともあれば、自然治癒するケースも少なくはありません。ジストニアのケースであれば、トリヘキシフェニジルで治療は可能となっています。この他、ケースによって治療法は変わることもあります。
不附随運動の初診に適した診療科目