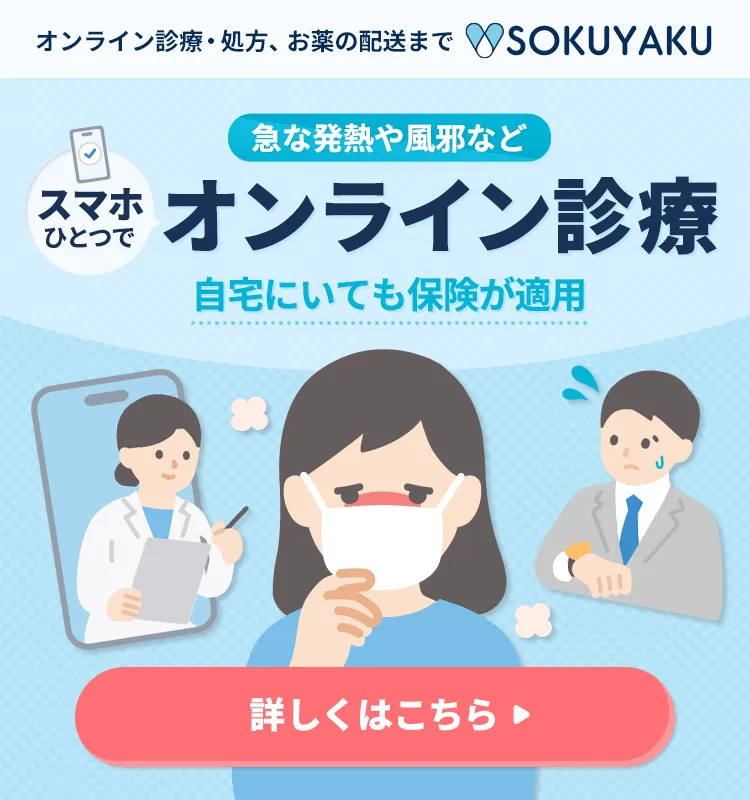真菌性髄膜炎はどんな病気?
真菌性髄膜炎という病気は感染症であり、クリプトコックス・ネオフォルマンスと言う真菌によって引き起こされます。この真菌は通常鳥類のフンの中などにあり、人の肺に空気中にある菌を吸い込むことで感染します。健康に問題のない人に菌が入り込んでもこの病気は発症しないことがあります。しかし、感染に対する免疫機能に障害のある人は、感染し頭痛や吐き気、発熱などを引き起こします。
真菌性髄膜炎の主な症状は?
真菌性髄膜炎のになると、全身が倦怠感に包まれたり、頭痛や吐き気、嘔吐、項部の硬直、発熱などの症状が現れます。またこれは細菌やウィルスによるものですので、それらが肺に入った場合、咳や痰が出たり呼吸困難になったりする場合もあります。ですが健康な人の場合ウィルスや細菌が肺に入ったとしても発症することは少なく、免疫機能が落ちている人がかかりやすいとされています。
真菌性髄膜炎の主な原因は?
真菌性髄膜炎の原因は、真菌が体内に入り込むことです。まず真菌は、鼻咽喉へ感染し、定着します。定着した部位から、鼻咽喉内にある傷口を通して、血液中に侵入します。血液中に入った真菌は、血流に乗って流れ、脊髄や髄液に入り込み、最終的には髄膜に達します。それによって、炎症がおき、発症してしまう仕組みになっているといわれています。
真菌性髄膜炎の主な検査と診断方法は?
真菌性髄膜炎は、髄液検査、CT、MRI、抗原抗体反応を主な検査方法としており、特に髄液検査は最も重要であるうえ、細菌検出が確定診断においても高い重要度を占めてきます。髄液中のクリプトコッカス莢膜の証明に、墨汁染色による検出が行われます。また、髄液圧の上昇により、細胞数やタンパク量の増加、糖分の減少など、結核性髄膜炎の類似所見を認めます。その他、頭部CTやMRIでは、水頭症の所見などがみられます。
真菌性髄膜炎の主な治療方法は?
真菌性髄膜炎の主な治療法としましては抗真菌薬のアムホテリシンB、ミコナゾール、フルコナゾール、フルシトシン、イトラコナゾールが使用されます。特に有効なのはアムホテリシンBの点滴静注で、始めは5~10mgから点滴し、日を増すことに0.5~1mgkg日まで増やしていく方法が取られます。またアムホテリシンBは単独でも効果的ですが、フルシトシンとの併用でより効果が出る事があります。
真菌性髄膜炎の初診に適した診療科目