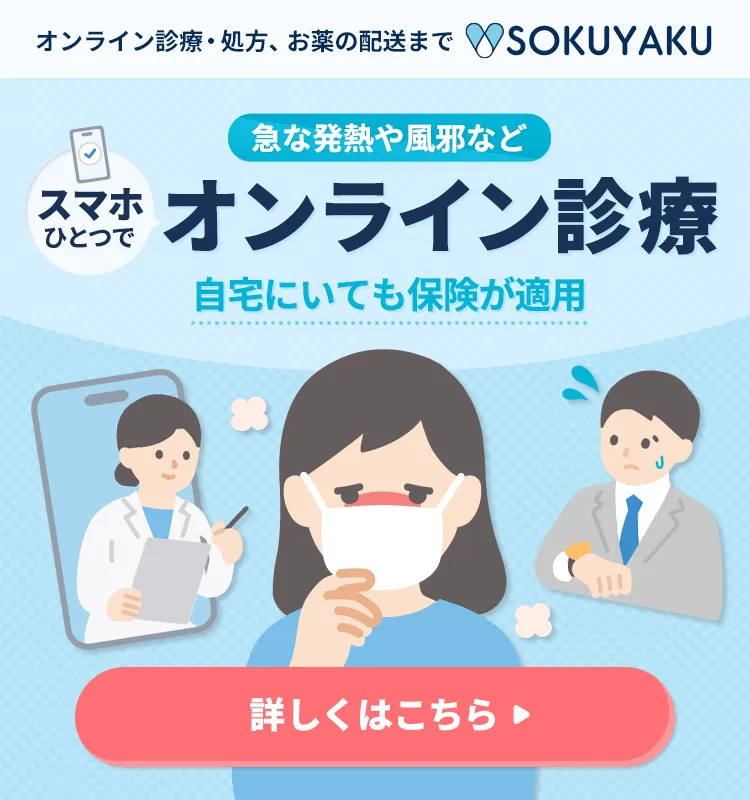尿失禁症はどんな病気?
尿失禁とは、自分の意思に反して尿をもらしてしまう病気の事です。女性は、解剖学的に尿道が短く、骨盤底筋の脆弱に伴い、40歳以上の4割以上に認められるとされますが、男性も前立腺肥大症の進行に伴い、その割合は徐々に増加します。
尿失禁症の主な症状は?
共通症状は、「尿が漏れてしまうこと」ですが、原因によりそのパターンは異なります。咳やくしゃみで失禁してしまう「腹圧性尿失禁」、突然の尿意に間に合わず失禁してしまう「切迫性尿失禁」、尿を出したいのに出せない、でも少しずつ漏れ出てきてしまう「溢流性尿失禁」、排尿機能は正常にもかかわらず、身体運動機能の低下や認知症が原因でおこる「機能性尿失禁」の4種類に大きく分類されます。また、これらが複合して生じる失禁を「混合性尿失禁」といいます。
尿失禁症の主な原因は?
尿失禁は、加齢による排尿機能低下はもとより、出産、排便時の強いいきみなどの過度の腹圧による骨盤底筋の衰えにより生じます。子宮脱、膀胱脱などの骨盤臓器脱や男性の前立腺肥大症の進行による前立腺部尿道の解剖学的変化によっても生じます。過活動膀胱、低活動膀胱は、脳梗塞や脳出血、パーキンソン病、脊柱管狭窄症といった脊髄神経疾患による二次的症状として尿失禁が認められることもあります。
尿失禁症の主な検査と診断方法は?
妊娠、出産回数、生活習慣を確認し、必要に応じ一回排尿量、一日排尿量、尿失禁量、排尿時間、間隔などの排尿日誌をチェックします。男性では、尿を出す筋力や、合併症についての問診と、前立腺の触診を行います。膀胱機能検査や、超音波を用いた残尿測定も行います。結石などの検査も行います。女性では、尿路感染の有無や尿漏れ量の検査、尿が出る角度などの測定を行い、症状を判断します。
尿失禁症の主な治療方法は?
女性の閉経後は、骨盤底筋の筋力低下が顕著となります。軽症の腹圧性尿失禁は骨盤底筋の訓練にて改善が見込めますが、良くならない場合には尿道の下にテープを留置するTVTもしくはTOT手術を検討します。骨盤臓器脱による場合には、腹腔鏡下仙骨固定術などの手術的治療が効果的ですが、術後に一過性の尿失禁を生じることもあります。切迫性尿失禁には、抗コリン剤やβ3作動薬などの薬物療法に加え、膀胱訓練も期待できます。前立腺肥大症では、その治療で失禁が改善することもあります。脳出血、パーキンソン病、脊柱管狭窄症が原因の場合はその治療も同時に行う必要があります。
尿失禁症の初診に適した診療科目