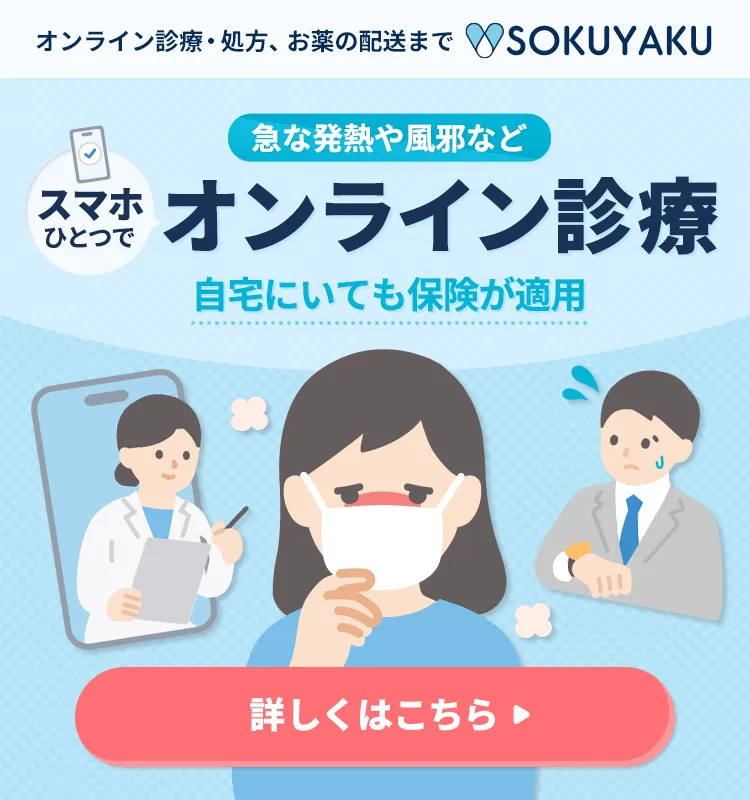脚気はどんな病気?
脚気は、ビタミンB1が欠乏して発症する全身倦怠感やむくみといった病気の事であり、現代ではめったにかかる病気ではありません。しかし、加工食品やアルコールの過剰摂取といった極めて偏った食生活をし続けると発症する可能性もあるので注意が必要です。ビタミンB1が多く含まれている食品は豚肉・枝豆等であり、ニラやタマネギといった野菜を同時に摂取するとビタミンB1の吸収が良くなります。
脚気の主な症状は?
脚気の症状は初期であれば食欲不振や全身のだるさ、とくに下半身がとても重く感じられます。そして次第にむくみやしびれ、息切れ、動悸、知覚や運動の感覚の麻痺などがあらわれます。
さらに進行してしまうと手足に力が全く入らず、寝たきりになってしまいます。
そしてそのまま病院にいかず放置してしまうと、心不全となり死に至る場合もあります。
脚気の主な原因は?
脚気はビタミンB1の欠乏が原因で起こります。ビタミンB1には、炭水化物をエネルギーに変換する補酵素としての作用と、神経機能を正常に保つ作用とがあります。食事による摂取量の減少、重労働や糖質過剰摂取による需要量の増加、アルコールなどによる吸収障害、肝障害による活性化障害などの要因でビタミンB1が欠乏すると、末梢神経症状として本症が引き起こされます。
脚気の主な検査と診断方法は?
よく知られた脚気かどうかの検査方法として、膝の下のくぼみをたたいて跳ね上がらないというのがあります。このときに全く反応がなければ陽性であることが多いです。これは膝蓋腱反射という人間だれもが持つ性質を用いた、有効な判定方法ですが現在診断を確定するものにはなっていません。
ビタミンB1が不足すると反射神経が鈍ってが鈍ってしまうのでそれを判断しているにすぎないのです。
現代においては血液検査でビタミンB1が欠乏しているか診断します。
脚気の主な治療方法は?
脚気の治療法としておこなわれているものはビタミンBの摂取をすることです。食事から積極的にビタミンBをとりいれ、サプリメントなどで補給する方法もとられます。白米にはビタミンBが足りないとので玄米食に変え、うなぎや豚肉などビタミンBが豊富な食材を選ぶようにします。
そしてビタミンBの体内への吸収を高めるアリシンが豊富なたまねぎやニラをあわせてとるようにします。
脚気の初診に適した診療科目
- 内分泌科 ( 内分泌科の病院一覧 )