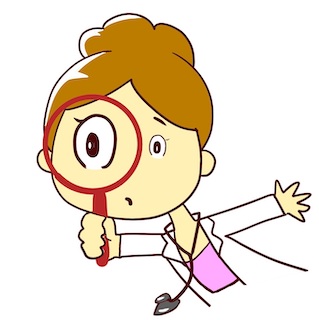今注目が集まっている医療や健康情報を病院検索ホスピタが厳選して分かりやすくお届け!今回は『 暗い場所でモノが見えにくい「網膜色素変性」とは? 』をご紹介させて頂きます。
網膜の細胞が「早く老化する」病気
「網膜色素変性」は、眼の中で光を感じる組織の「網膜」に少しずつ異常があらわれる病気です。「網膜」は、眼球のいちばん内側(後ろ側)にある約0.1~0.4mmの薄い膜で、カメラに例えるとフィルムの役割をしています。
私たちの目から入る光は、角膜 → 前房 → 水晶体 → 硝子体を通って「網膜」で焦点を結びます。網膜には、光を感知する「視細胞」と呼ばれる細胞が約1億個集まっています。網膜に届いた光は、視細胞で電気信号に変換され、その情報は「神経線維」から「視神経」へと伝わって脳に送られ、視覚が認められます。
「網膜色素変性症」は、視細胞が早く老化して、その働きが鈍くなる病気です。老化した視細胞は光を感じられず、映像を捉えることができなくなります。遺伝性による難病で、国内では、約3000~8000人に1人の割合で発症するといわれています。個人差はありますが、ゆっくりと長い年月をかけて緩やかに進行する病気です。

暗いところで「ものが見えづらい」
「網膜色素変性症」の症状は、おもに
(1)夜盲
(2)視野狭窄(しやきょうさく)
(3)視力低下
の3つが挙げられます。病気が進行するにしたがって、この順番で症状があらわれるのが特徴です。
「夜盲」とは、いわゆる鳥目と呼ばれる症状で、夜間や暗いところでものが見えにくくなる状態です。「視野狭窄」は、視野が縁のほうから(あるいは不規則に)欠けて、見える範囲が狭くなる症状です。そして、病気の進行とともに視力が低下します。重症化すると失明する恐れがあります。これらの症状は急に起こることはほとんどありません。数年かけてとてもゆっくり進行するのが特徴です。

最近「つまづきやすい」と感じたら
網膜の視細胞にある光を感じる組織は、「杆体細胞(かんたいさいぼう)」と「錐体細胞(すいたいさいぼう)」の2種類があります。「杆体細胞」は、光に関する感度が高く、暗い場所でのわずかな光からものを感知することができる細胞です。一方「錐体細胞」は、光の感度はそれほど高くはないですが、明るい場所で色を感知する働きがあります。
網膜色素変性症では、はじめに「杆体細胞」の働きが弱くなります。そのため、夜盲や視野狭窄が起こりやすくなります。そして、病気が進行に伴って「錐体細胞」の機能が失われ、視力の低下につながります。
初期の自覚症状では、夜盲よりも視野狭窄で異変に気づく人が多いようです。視野の範囲が狭くなることで、
(1)つまづきやすくなる
(2)人や物にぶつかるようになる
(3)スポーツでボールを見失うことが多い
といった様子をくり返すようなら、網膜色素変性症の疑いがあります。
原因のほとんどは「遺伝子」の異常
網膜色素変性症の原因は、ほとんど「遺伝子異常」と考えられています。両親から受け継いだ遺伝子のどちらか1つに特有の変異(傷)があるときに発症しています。原因となる遺伝子は、現在のところ40種類以上は見つかっていますが、その遺伝子によって、網膜色素変性症が必ず発症するとは限りません。
親から子どもへは、約50%の確率で遺伝するといわれています。男女差はありません。発症年齢には個人差があり、幼少時に症状があらわれる人もいますが、40歳を超えて自覚症状を訴えるケースも少なくありません。
網膜色素変性症は、いまだに分からない部分の多い病気です。明らかな原因遺伝子として報告されているのは、原因の一部と考えられており、原因の多くは現在のところ不明です。各国の機関によって研究が進められている段階です。

現在まで「根本的な治療」が見つかっていない
暗いところで見えづらい、視野が狭く感じるといった症状がみられたら、早めに「眼科」を受診し、専門医に相談しましょう。病院では、眼底検査、暗順応検査、視野検査、網膜電図などを行ったうえで診断が確定します。
遺伝子が関係しているため、根本的な治療法は今のところ見つかっていません。病気の進行を遅らせる治療をはじめるのが一般的です。治療用のサングラスを着用し、「ビタミンA剤」や「網膜循環改善薬」などを服用する薬物治療が中心になるでしょう。長時間の屋外活動を控えるなど生活の工夫も必要になります。
世界中で行われている治療法の研究成果が待たれます。厚生労働省による医療費助成制度を受けることができます。詳しくは、病院や保健所で確認するとよいでしょう。