今注目が集まっている医療や健康情報を病院検索ホスピタが厳選して分かりやすくお届け!
今回は『薬の副作用と起こる「薬疹」について』をご紹介させて頂きます。
「全身に左右対称」の発疹が出たら?
薬疹とは、薬を内服したり注射したりしたあとの副作用によって起こる発疹です。病院から処方された薬や、市販されている薬を飲んだあとに、
(1)全身がかゆい
(2)思いあたらない発疹が出た
というときは薬疹の可能性があります。
全身あるいは体の広い範囲に発疹が左右対称にあらわれるのが特徴です。発疹の種類は、おもに次の3つに分類されます。
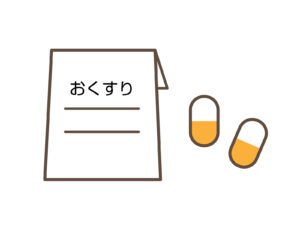
・紅斑丘疹型(赤く小さなブツブツの発疹)
・多型紅斑型(いろいろな形の赤い発疹)
・紅皮症型(全身が均等に赤くなる発疹)
「遅れてあらわれる」アレルギー反応
薬疹は、軽いかゆみ、吹き出物のような軽症から、皮膚全体がやけどのようにただれるといった重症なものまで、症状はさまざまです。これらの症状の大半は、薬による「アレルギー反応」です。したがって、誰にでも起こる反応ではありません。症状があとからあらわれることから「遅延型」と呼ばれるアレルギーです。

薬の用法や容量を守って正しく服用していたとしても、症状が出てしまうことはあります。そのため、基本的に薬疹の予防は難しいといえるでしょう。しかし、一度薬疹があらわれた薬を記憶(記録)しておくことで、症状を回避することはできるでしょう。
服用から「1〜2週間」が注意!
薬疹は、薬を飲んですぐに出ることはあまりありません。通常は服用から約1〜2週間して、反応がある場合は症状があらわれます。それまでは、体の免疫機能が発疹の原因となる物質(アレルゲン)と戦うための準備を整えているのです。
免疫機能が発疹の原因である薬と戦うための準備を「感作」といいます。薬疹があらわれるまでの、約1〜2週間かかる期間を「感作期間」と呼びます。薬疹が出た場合、ほとんどの薬に感作期間があることを考えると、薬疹が出た食前に飲んだ薬は原因ではないことが予想されます。
薬疹が「起こりやすい薬」とは?
体の免疫機能が、「敵」とみなした薬が2度目に体内に入ると、免疫細胞が、アレルギーを引き起こします。一度薬疹を起こした薬は、次の服用でも発疹があらわれる可能性が非常に高いと考えられます。そのため、
(1)発疹はいつ出たか
(2)約1〜2週間前にどのような薬を飲んだのか
をよく思い出して書き留めておくことが大事です。
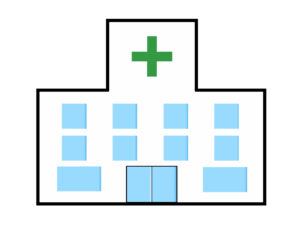
今はたくさんの種類の薬が開発されています。そのなかでも薬疹を起こしやすいといわれる薬は、順番に
(1)抗菌剤(抗生物質)
(2)消炎鎮痛剤
(3)高血圧治療剤
(4)抗腫瘍剤
と報告されています。
皮膚症状だけであれば「皮膚科」
抗生物質の服用には注意が必要です。服用してから体に異変がないか全身をよく観察しましょう。病院で処方される抗生物質は、主に次の5つです。
・ペニシリン系
・セフェム系
・ニューキノロン系
・マクロライド系
・テトラサイクリン系
このなかで、ペニシリン系、セフェム系、ニューキノロン系の抗生物質は薬疹を引き起こすことがあるとされています。通常、発疹の原因となる薬の服用を中止すれば、症状は約1~2週間で軽快します。
皮膚症状だけであれば皮膚科を、体がだるい、発熱があるなどの症状をともなうようなら内科、アレルギー科を受診しましょう。
