今注目が集まっている医療や健康情報を病院検索ホスピタが厳選して分かりやすくお届け!
今回は『これから山の季節、高山病の予防策 』をご紹介させて頂きます。
山では、体の「適応」が大事
山ガールのブームは落ち着いたようですが、それでも近年、登山やトレッキングを楽しむ女性は増えています。また、登山にかぎらず、本格的なアウトドアに挑戦する家族の姿も年々多く見られるとのことです。
これから夏に向けて、山歩きなど自然に触れる機会は増えるでしょう。高地(標高約1500メートル以上)で大事なことは体の適応です。

高地では、空気中の酸素濃度が薄くなるため、一般的に体が適応するには時間が必要です。環境にうまく適応できないと「高山病(高度障害)」が起こりやすくなります。別名「低酸素症」や「山酔い」ともいわれる病気です。
高山病は、頭痛だけじゃない
酸素の薄い環境では、血液中の酸素濃度が低下し、体が酸欠状態に陥りやすくなります。普段と同じように呼吸しても、血液に取り込める酸素の量が減るからです。
標高2500メートルまで登ると、約25%の人に高山病の症状が出るといわれています。さらに、標高3500メートルを越えると、ほとんどの人が何らかの症状があらわれるようです。
標高3776メートルの富士山の頂上では、平地の約60%の酸素しかないため、体内への酸素量は平地のおよそ半分に減ってしまいます。そこで「半分の酸素」で体を動かさなければなりません。その環境に適応できるかどうか、できないときに、次のような症状があらわれます。

・頭痛(頭が重く、振ると痛む)
・胸部の圧迫感
・吐き気、食欲不振
・腹痛(腹部の不快感)
・疲労感、脱力感
・顔、手足のむくみ
・めまい、ふらつき
・睡眠障害
だいたい「頭痛」は起こる…
高地での低酸素に対する体の変化は、ほとんどの人に起こります。高山病の症状は人によって差が大きく、登山の経験によって多少軽減するとの意見もありますが、そのメカニズムなどは明らかになっていません。しかし、若い人にくらべて高齢者は、低酸素状態になりやすいようです。
高山病は、急に襲ってくるわけではなく、兆候があらわれる病気です。その1つが「頭痛」です。脳は体の中でもっとも酸素を消費するため、低酸素状態に弱く、高地では頭痛が起こりやすくなります。
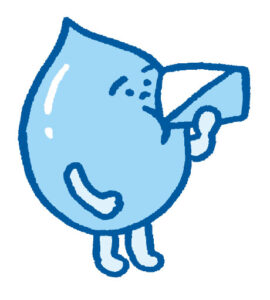
「頭が重い」、「頭を振ると痛む」などの症状は高山病の兆候です。注意信号として捉えることが大事です。症状が出たときは、それ以上登るのをやめて休息をします。また、頭痛薬を持参するなら、眠くならないものを用意します。
高山病を「予防する」心がけ
楽しい登山で辛い思いをしないために、高山病を予防するために次のような心がけを行うとよいでしょう。
<計画は「ゆるめ」に>
無理な計画を立てずに、時間をかけて少しずつ高度を上げて、体が低酸素に慣れやすいようにしましょう。
<水分補給はたっぷりと>
高地では体が適応しようとして平地より水分を失います。すると怖いのは脱水症状です。水分はたくさん摂りましょう。高地では、喉が渇く感覚も鈍くなりがちです。ふだんの約1.5~2倍の量を摂取します。
<お腹で深呼吸する>
高地では呼吸は「早く浅く」なります。お腹を使って十分に息を吸い込むように深呼吸すると、体内に入る酸素量は増えます。ベルトをゆるめにして、ゆっくり腹式深呼吸をしましょう。
