今注目が集まっている医療や健康情報を病院検索ホスピタが厳選して分かりやすくお届け! 今回は『秋の花粉症、そろそろ予防と対策!』をご紹介させて頂きます。
わずか50年で「国民病」にまで発展
現在、日本には約3300万人の花粉症患者がいるといわれています。これは国民の約26.5%にあたる数字です。花粉症患者の多くはスギ花粉症で、日本では1964年(昭和39年・東京オリンピック開催の年です!)に、はじめてその症状が報告されています。
そして、1980年代に入ってから、スギ花粉症は猛烈なスピードで患者数を増やし、花粉症といえば、スギやヒノキなど春になると世間の話題を独占しています。症状が報告されてから50年で、花粉症はいまや「国民病」と呼ばれるようにまで広がっています。
秋の花粉症は「雑草」の花粉
日本には、約60種類の植物花粉が花粉症を引き起こすと考えられています。厚生労働省が行った調査によると、目のかゆみ・くしゃみ・鼻水など花粉症の症状が出る期間を「9〜11月」と答えた人は、全体の約15%におよびます。これは「草本花粉」が原因の「秋の花粉症」と考えられます。
夏から秋に(1)目のかゆみ・(2)くしゃみ・(3)鼻水・(4)鼻づまりなど、花粉症の症状が出たら、それは「草本花粉」の花粉症かもしれません。草本花粉は、イネ科やキク科など背が低く、私たちの生活範囲で自然に繁殖する、いわゆる雑草の花粉です。
ススキやアシなど、イネ科の花粉は7ヶ月も飛ぶ
イネ科の植物は「夏から秋の花粉症」として注意が必要です。種類によって飛散時期に異なるため、4〜10月の長い期間にわたって花粉が飛散します。症状は、目のかゆみ・くしゃみ・鼻水のほか「咳がでる」「皮膚のかゆみが全身に出る」「やや高めの発熱」「体がだるくなる」のが特徴です。これは「枯草熱」と呼ばれる症状です。
おもな植物は次のとおりです。
・イネ
・カモガヤ
・ギョウギシバ
・ハルガヤ
・ススキ
・アシ
イネ科花粉症は、食物アレルギーに気をつけて
イネ科花粉症患者は、食物アレルギーを併発することがあります。イネ科花粉症による食物アレルギーの症状は、皮膚に赤み・むくみ・蕁麻疹(じんましん)がまず起こります。症状が重くなると、下痢や嘔吐をくり返します。アナフィラキシーショックを起こして意識がなくなる患者もいます。
内科、アレルギー科などの専門医に相談したうえで、次の食べ物を口にするのは控えるがよいでしょう。
・小麦
・トマト
・メロン
・スイカ
・ジャガイモ
・オレンジ
・セロリ
・バナナ
原因食物(アレルゲン)食べてから2時間以内に症状があらわれる「即時性」、6〜8時間後に症状があらわれる「遅発性」、数日後に発症する「遅延型」があります。アレルギー検査をして、自分の対処方法を知っておくことが大事です。
キク科植物は、全国に広く生息している
日本で最初の花粉症は、キク科の植物の花粉によるものでした。ブタクサ花粉症が、スギ花粉症より3年早い1961年(昭和36年)に報告されています。
キク科の植物は、道端・空き地・公園・畑・土手沿い・河川敷・学校周辺の緑地など全国に広く生息しています。スギやヒノキの花粉症のように、鼻や目に苦しい症状が起こります。
おもな植物は次のとおりです。ブタクサはおもに太平洋側に、ヨモギは日本海側に多く生息するといわれています。
・ブタクサ
・オオアワガエリ
・ヨモギ
・オオブタクサ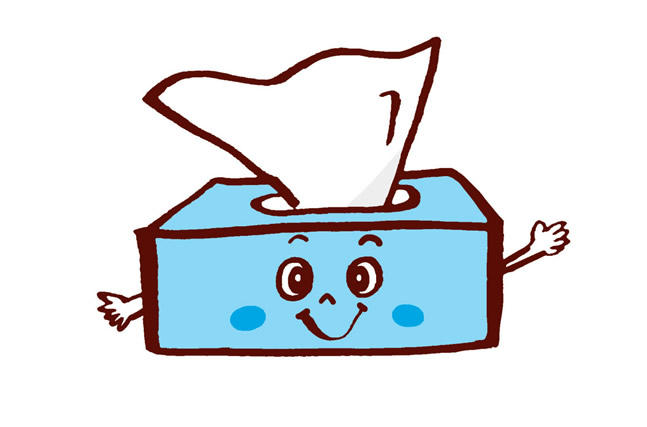
「秋の花粉」の対策と治療
スギやヒノキの樹木は丈が高いため、その花粉は風に乗ると200kmも飛散するといわれますが、草本植物は30〜50mの範囲で広がります。そのため、イネ科やキク科の植物が生えている場所に近づかないのが、花粉症の対策にはもっとも効果的です。
冬から春にかけて、花粉が飛散しない時期に、散歩がてら、近所の植物生息の環境をよく確認しておき、「花粉の飛散時期は近づかない」「通勤や通学路に生息する場合は迂回する」などの工夫が必要です。
予防と治療は、「春の花粉症」と同じです。(1)外出時にはマスクや眼鏡を着用する(2)風がある日は、窓を閉めておく(3)家に入る時に服をはらう(4)定期的に家を換気する、などが挙げられます。症状が出ているときは、抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬、点鼻薬などを処方してもらいましょう。
