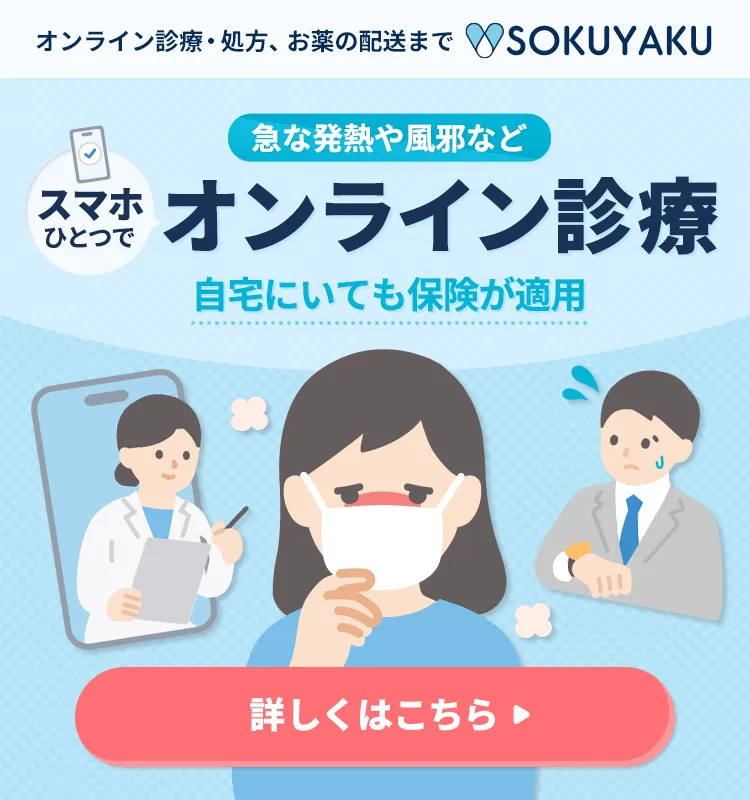脊髄小脳変性症はどんな病気?
脊髄小脳変性症とは神経系の難病の一種で、特定疾患に指定されている疾患です。後頭部の下側にある小脳と、小脳につながる脊髄などに異常が起こることで発症します。
歩行時のふらつき、手の震え、ろれつが回らないなどが典型的な症状で、これらの症状は運動失調と呼ばれます。
脊髄小脳変性症は遺伝子変異によって発症する場合もありますが、原因がわからずに発症する場合もあります。全体の約3分の1が遺伝子以上によるもの、残りの3分の2は非遺伝性のものです。非遺伝性の多くは成年期に発症する孤発性脊髄小脳変性症です。孤発性脊髄小脳変性症には小脳の運動失調症状だけが現れるものと、手の震え、尿失禁、失禁なども症状として現れるものとに分けられます。
脊髄小脳変性症は原因に応じて分類されており、病型が多数存在します。
現段階では根本的に治療する方法は見つかっておらず、症状にあわせた支持療法が行われます。症状の出現様式にも個人差があります。
脊髄小脳変性症の主な症状は?
脊髄小脳変性症では、共通して起立や歩行がふらつく、手がうまく使えない、喋る時に口や舌がもつれるなどの症状が現れます。これは小脳や脊髄が体幹、言葉の抑揚、筋力のバランスなどに関わる重要な役割を担っているためです。
これらの運動が上手に出来ない症状を総称して運動失調症と言います。症状はゆっくりと進行します。
脊髄小脳変性症として総称されている病気の中にもさまざまな種類があり、運動失調以外の症状を伴うものもあります。基本的に筋肉をバランスよく使うことができなくなるため、字を書くなどの細かい動作が困難になります。足の突っ張り、手の震え、眼球の揺れ、筋力低下などの症状が現れたり、自律神経系に影響が及ぶと呼吸や血圧の調整機能も障害されます。その他にも末梢神経の障害に関連するしびれ、幻覚や失語、失認、認知症などの高次機能障害が現れることもあります。
症状が悪化した場合、食物の飲み込みや排尿排便に影響を及ぼす場合もあります。嚥下機能に異常が現れると誤嚥性肺炎や呼吸障害につながる恐れもあります。
脊髄小脳変性症の主な原因は?
脊髄小脳変性症の原因は、遺伝性と非遺伝性の大きく二つに分類でき、さらに原因遺伝子は現段階で40以上存在するとされています。遺伝性の脊髄小脳変性症は全体の約3割程度で、その中でも常染色体劣性遺伝形式、常染色体優性遺伝形式に分けられます。
劣性遺伝形式は日本においては少数であり、多くは小児期など早くから発症することが多いです。
一方優性遺伝形式の場合はより頻度が高く、3型、6型、31型、赤核淡蒼球ルイ体萎縮症などの種類があります。
優性遺伝形式では高確率で親から子供に遺伝しますが、劣性遺伝形式ではまれに孫へ遺伝するケースが確認されています。
これら二つとも異なる遺伝性を示さないタイプの脊髄小脳変性症は孤発性脊髄小脳変性症と呼ばれます。発症原因は明らかになっていませんが、小脳や脳幹に異常たんぱく質が蓄積し、萎縮を来すために発症すると考えられています。孤発性脊髄小脳変性症には多系統萎縮症と皮質性小脳萎縮症などの種類があります。
脊髄小脳変性症の主な検査と診断方法は?
脊髄小脳変性症の診断を行う場合、まずは問診によって症状や経過、小脳と脊髄系の病歴がないかなどを確認し、同時に身体所見なども確認した上で必要な検査が行われます。多くの場合頭部MRIやCT検査などの画像検査が行われます。この検査では小脳や脳幹、大脳基底核や大脳皮質の萎縮を確認できる場合があります。
また核医学検査では小脳の血流、ブドウ糖の代謝、心臓の交感神経などの異常についても調べることができます。
また、ビタミンB1やB12、葉酸の欠乏、アルコール中毒、甲状腺機能低下症、多発性硬化症、エイズによる神経疾患などは脊髄小脳変性症と症状がよく似ているため、これらの可能性を除外していくための検査も必要です。遺伝性を伴うケースもあるため、必要に応じて遺伝子検査を行い、原因となっている遺伝子変異を探します。
要件を満たしている場合には、脊髄小脳変性症は指定難病申請が可能です。医療費助成が受けられるため重症度を分するための検査も行われます。
脊髄小脳変性症の主な治療方法は?
脊髄小脳変性症の根本的な治療法は見つかっていません。症状の出方や進行のスピードにも個人差があるため、現れる症状に合わせた支持療法を行うことが重要です。
特に運動失調に対しては、甲状腺刺激ホルモンを増やす内服薬を用いることで一定レベルまでは改善が期待できます。
パーキンソン病の症状が現れている場合にはドーパミン不足を補う薬を併せて用いることもあります。
脊髄小脳変性症は進行ととも徐々に筋力が低下していくため、リハビリテーションを行うことで筋力低下を防いだり、現在の筋力を保つように努めることは特に重要です。
ある程度の筋力が保持できれば寝たきりになってしまう可能性を減らすことができ、ふらついたとき物につかまったり、転倒などを防ぐことにも繋がります。
筋肉は骨格を支えているため萎縮すると脱臼などの合併症を引き起こす場合もあります。
また、食べ物が飲み込みにくくなることから発症する誤嚥性肺炎にも注意が必要です。
食材を細かく刻んだり、とろみをつけるなど食事形態に注意を払い、口腔ケアも重要です。発症した際には、抗生物質を用いた治療が行われます。
脊髄小脳変性症の初診に適した診療科目
- 神経内科 ( 神経内科の病院一覧 )