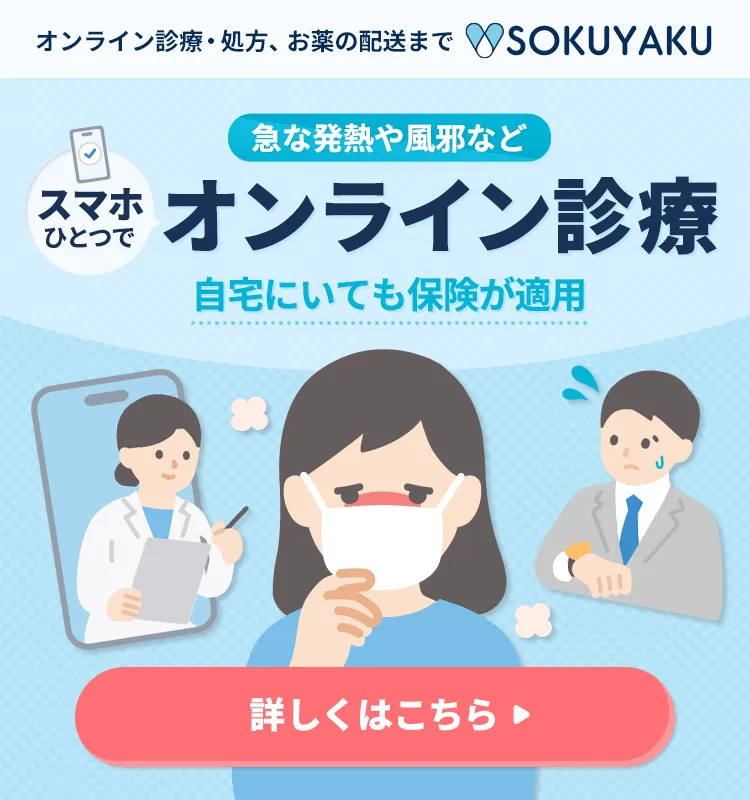犬回虫症はどんな病気?
犬回虫症とは、イヌ回虫の卵が何かの原因で人間の体内に侵入し幼虫のまま体内を移行して内臓や眼に入り、様々な障害を引き起こす疾患です。幼虫移行症とも呼ばれています。回虫は代表的な寄生虫の一種で、犬回虫は犬の消化管に寄生している回虫を指します。
人の体の中では幼虫から成虫になることはできず、成虫になるためには猫や犬、他の動物が宿主として必要です。
犬回虫が人に感染するケースとしては飼い犬に触れたり、犬猫が排便する公園の砂場や草叢などにある虫卵を何らかの経路で触れ、経口摂取に至った場合や、子犬に口をなめられるなどの例が挙げられます。回虫卵は腸内で孵化し、腸壁から侵入し血流にのって全身に運ばれ、肝臓、リンパ節、肺、脳などさまざまな組織に入り込みます。
動き回る幼虫は幼虫内臓移行症を引き起こし、全身症状や命に関わる症状を生じることもあります。
治療には駆虫薬が用いられます。適切に治療が行われれば完全に駆除が可能です。
犬回虫症の主な症状は?
犬回虫症を発症すると現れる症状としては発熱や全身の倦怠感、食欲不振などがあげられます。また稀な例ではアレルギー性の発疹、胸痛、肝臓の異常、てんかん様発作、しびれ、麻痺などが起こり、眼に入ると、視力の低下、眼の痛み、視界に虫のようなものが飛んで見える飛蚊症なども現れます。
症状は大きく分類すると内臓移行型と眼移行型に分けることができます。
回虫は本来人を宿主としない寄生虫のため、人の体内に侵入しても成虫になることができません。
そのため人に侵入した回虫は幼虫のまま全身のさまざまな臓器に侵入し、それらの臓器に関連する症状が現れます。回虫が侵入してから症状が現れるまでは約1ヵ月程度を要する場合が多いです。幼虫はまず腸管の粘膜から血液に入り、リンパによって運ばれます。
肝臓から肺へと移動する際には肺炎や肝炎、網膜の中に移る際には眼内炎、膜炎などを生じます。
目に関連する症状には特に注意が必要で、重症な場合には失明に至るケースもあります。
犬回虫症の主な原因は?
犬回虫症は、寄生虫である回虫を原因に引き起こされる疾患です。犬に寄生していた回虫が誤って人の体内に入ると、幼虫のまま体内の至る場所へ移行する、幼虫移行症と呼ばれる状態になります。
移行した臓器によってさまざまな障害を引き起こすのが特徴です。
感染経路としては主に犬の糞便や、糞便が見られる場所に触れて手を洗わずに食べ物を摂取した際に感染するケースが挙げられます。
具体的には公園の砂場、海岸、草叢、庭などは感染リスクが高い場所と言えます。またニワトリのレバーの生食を摂取し、肝臓に潜んでいた幼虫を同時に摂取してしまうケースや、仔犬に口を舐められた際に、気管や食道にいた回虫を摂取してしまうケースも例として挙げられます。
幼虫移行症は犬回虫に限らず、人以外を終宿主とする寄生虫が幼虫のままで人の体内を移行する症状を指すもので、原因寄生虫にはネコ回虫、アニサキス、動物由来の鉤虫などさまざまな種類が挙げられます。
犬回虫症の主な検査と診断方法は?
犬回虫症は血液検査、X線検査、超音波検査などの検査が行われ、確定診断に至ります。血液検査では寄生虫に対する抗体や白血球の一種の好酸球の増加などを調べることができます。
抗体とは体を寄生虫などの攻撃から守る役割を果たすタンパクです。また肺の炎症、肝臓の腫大、発熱などが生じている場合、血液検査の結果も含めて回虫症が疑われます。
また血液検査においてトキソカラ属線虫の抗体が認められた場合には回虫症の診断が確定します。
X線検査、超音波検査などは症状が現れている部位をより詳しく調べる場合に必要に応じて行われる検査です。
また、臓器の一部の組織を採取して生検を行う場合もあり、これは幼虫による炎症の有無、幼虫の形跡を調べる目的で行われます。
また、飼い犬が犬回虫症に感染していると疑われる場合には、ペット専門の医療機関で糞便検査によって犬に対しても診断が行われます。
犬の回虫症の場合、回虫を吐いたり、糞便中に回虫が混ざるなどのほか、下痢、食欲不振、体重減少などが症状として現れます。
犬回虫症の主な治療方法は?
犬回虫症に対しては、症状が自然に改善することが多いため軽度の症状であれば積極的な治療を行わず、経過観察となることも多いです。症状が現れている場合は駆虫薬の投与が主な治療方法となります。目安として3週間隔で2回駆虫を行うのが一般的です。
ほとんどの場合2回で完全に駆除が期待できます。ただ体内を移動している一部の回虫には効果が見られない種類の薬も存在します。
また眼の症状に対しては光凝固療法が用いられます。これは強い光線を照射することで眼の中にいる幼虫を殺す方法です。
ただ基本的に体内の組織内に寄生した幼虫に対しては確実な治療法はありません。
回虫は産卵数が非常に多く、その処理を外界で行うことは困難とされています。
予防のためにはまず飼い犬に対し、定期的に虫下しの治療を行うことが重要です。
排泄したばかりの便を処理する際には手に触れないように素早く処理し、処理後は手を洗って清潔を保つ必要があります。
調理の際なども清潔を保つことで食事を共にする同居者への感染を防ぐことに繋がります。
犬回虫症の初診に適した診療科目
- 内科 ( 内科の病院一覧 )
- 眼科 ( 眼科の病院一覧 )
- 感染症内科 ( 感染症内科の病院一覧 )